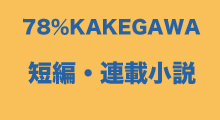 |
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
掛川を舞台に繰り広げられる、ある若者の青春時代。
この主人公は、ひょっとしたらあなたかもしれない…。 |
|
| 連載小説「初恋-1」 |
|
|
|
|
1981.3 No.12号掲載
|
|
|
|
|
作:あらかわじゅんじ
|
|
彼女と私は、中学一年の時に、初めて巡り合った。同じクラスになった私と彼女の席は、日当たりの良い窓際の列の、一番後ろに彼女。そして、その前の席が私だった。当時、彼女は、国語・英語が得意で、成績も、学年のトップクラスにいた。彼女は、同じクラスの中にあって、他の女性とにはない、貴品のある顔立ちをしていた。そんな彼女の、気取りのない貴品と聡明さに、私は憧れていた。否、憧れというよりは、もしかしたら、自分では気付かずにいた、恋だったかも知れない。
その頃の彼女は、私に何か話があると、私の背中を、ちょんちょんと軽く指先でつついて合図をしてきた。私には、その彼女の指先の感触が、とても快いものであった。そして、私が後ろを振り向くと、楽しい雑談をしたり、時には苦手な教科を教え合ったりもした。とはいっても、私が教えてあげる事のできる教科は数学だけで、他の教科はほとんど彼女の方から教えて貰うことが多かった。
二年、三年と、私も彼女も進級していったが、到頭、後の二年間は、彼女と同じクラスにはなれなかった。その間、私は、廊下で彼女と擦れ違ったりもしたが、これといって別に話もしなかった。文化祭や体育大会の時なども、彼女を遠くから眺めているばかりであった。それで、その頃には一年の時の彼女との楽しかった会話も、私には夢だったのではないかと思われ、彼女を遠い世界の人のように感じていた。それでも私は、いつも遠くから眺めていた彼女の美しい姿に、恋をしていた。
中学三年の三学期も終わりに近付くと、就職する人、進学する人、進学する人は何処の学校を受験するか、進路を決める時期に入っていた。そんな三学期も終わりに近づいたある日、進学希望の生徒を講堂に集め、受験する高校別に列を作り、私はA高校を受験する事に決めていた為、一番先頭にA高校と書かれたプラカードを持って立っていた先生の列の後ろに並んだ。まるで、高校野球の開会式の様であった。
生徒たちは列を作りながらざわめいていた。その中で、ふと気がつくと彼女も私と同じ列に並んでいるではないか。私の憧れの人が、何を隠そう、今同じこの列に並んでいる。その人の名は、親子という名で、みんなからは「親子、親子」と親しく呼ばれていたが、親子程年は老けていなかったと、作者は書いているが、作者自身も何を書いているのかわからない。とにかく、私の名まえは、真(まこと)と申します。
「やあ、暫くだなあ。」と、私が親子に向かって笑顔を見せると、「な〜に、いやだ、真君も同じ高校受験するの。」と、怪訝そうな顔で、私を見つめていた。その怪訝そうな彼女の表情の奥に何があるのか、私は不安であった。とは思ってみたものの、彼女と同じ高校を私も目指しているとわかった時には、一層その高校に進学したい、という気持ちに駆られた。
いくら無神経な私でも、合格者発表の数日前から不安は募るばかりであった。果たして合格するのだろうか。情けない私は、合格発表の当日、A高校の校庭に出される、合格発表の掲示板を見に行くことさえできずにいた。母が代わりに、その掲示板を見に行った。彼女も私も、無事A高校に合格していた。親子の合格の知らせは、幼馴染みの真弓から聞いた。 (つづく) |
|
| 連載小説「初恋-2」 |
|
|
|
|
1981.4 No.13号掲載
|
|
|
|
中学時代、私は半ば、受験勉強に責められ、反面、親子に対する片思いに悩まされ、苦渋に満ちた生活を送った。そして、なんとか無事に中学を卒業すると、高校へ通い始めるまでの、束の間の春休みに入った。私は、春休みになったら、私の一番の親友である五郎と、町へ遊びに行く約束をしていた。「ある朝、僕は店のおじさんと…」と、私が目醒めると、テレビの子供番組で、泳げたいやき君の歌が聞こえてきた。その日は五郎と町へ遊びに行く約束の日であった。
午前九時頃家を出ると、五郎の家に行った。彼の家は、大地主で、多くの小作人を抱えて大層栄えていたらしい。その名残が今も、大きな門や石垣、白壁の立派な米蔵が残っていた。彼は、休みの日になると朝寝坊であった。私は、彼の家の門をくぐり抜け、玄関の前で立ち止まると、「お〜い、五郎居るか」と、大声を出して五郎を呼んだ。すると彼は二階の窓から、寝惚け眼で顔をのぞかせた。まるで、素っ頓狂な蛸のようであった。
「お〜、悪い悪い、寝坊しちまってよ。今降りて行くから。」と言って、二階の窓を閉めたが、彼は慌てていたのか、顔をのぞかせたままで窓を閉めた為、かれの首は、窓のガラス戸とガラス戸の間に挟まれて、痛がっていた。五郎が玄関から出て来るのを待って、町へ出ていった。一緒に歩き出し、彼の首を見ると、赤く腫れていた。私は、彼の自尊心を傷つけまいと、何気ない素振りで一緒に歩いていたが、内心、笑いを堪えるのに四苦八苦していた。
朝十時頃、町の繁華街に出て、レコード店に入ったり、町で一番大きな店舗を構える平喜(掛川に実在した店、今はない)に入って、奥の玩具売り場で遊んだ。
私は、普通科の高校へ進学し、五郎は工業高校へ進学した。幼馴染みの二人は、幼稚園時代から、ずっと一緒に通学してきた。しかし、これからは、別れ別れになってしまう。私は、それが寂しかった。「これからは別々の学校に通うんだなあ、俺たち。」と、つぶやくように私が言うと、「そうだなあ。」と、五郎も頷いた。でも、お互い希望の高校へ進学できて、ほっとした春休みであった。
遊び廻っているうちに、昼のサイレンが、掛川公園の山頂で鳴り始めた。二人は、おなかもすいてきていたので、食堂に入って両親から貰った小遣いで食事をした。その食堂は連雀にあって、その食堂から親子の家はすぐ近くにあった。私は、何故か、その食堂で親子丼を食べた。食堂は二階に有ったが、窓からの眺めはあまりよくなかった。(この食堂も当時は営業していたが、今はない。)
そうそう忘れていたが、親子は、高校進学のお祝いに両親から「聖子」という名まえを貰ったそうで、そのことで彼女は、町の話題になっていた。(それで以降、親子のことを、文中では、改めて聖子と呼ぶことにした。)
食後、五郎が、「本屋に行こうぜ。」と、言い出した。彼の言葉は、受験勉強からの解放感の為か、生き生きしていた。「いいよ、行こうか。本買うのか?」「別に買いに行くんじゃないけど、いいだろう。」書店は、この食堂の斜め向かいにあった。お金を支払って食堂を出ると、通りを渡って本屋に入った。 (つづく) |
|
| 連載小説「初恋-3」 |
|
|
|
|
1981.5 No.14号掲載
|
|
|
|
書店に入ると五郎は、「スクリーン」という映画雑誌を手に持って、頁を開いた。
「真、こいつ知っているか。」と、言いながら五郎は、その本のグラビアを指した。
「知らんけど、すげえ、いい女だな。」
「今、こいつ人気あるんだぜ。」
五郎の指さしたその外人女優の写真を見て、私は、新たな女性へのセンスを学ぶ思いがした。五郎はそう言い終えると、その本のページをめくって、熱心に見ていた。
書店は、十坪位の、奥に細長い小さな書店であった。出入口処には、レジ係の女性が居た。壁の周囲には、全集や単行本、専門分野の本が、整頓よく並べられていて、店内中央には週刊誌や文庫本が本棚に集まり、その周辺を廻ることができるようになっていた。また、一番レジに近い処には、大人の膝あたりまでくる台が有りそこには、月刊の文学雑誌や週刊誌、その当時の人気作家の単行本が並べてあった。まだ、その頃は、ビニール本などという私にとって、俗悪で大好きな本は、出回っていなかったし、本の自動販売機等もなかった。最も世間やマスコミで取り上げなかっただけの話で、実際は、私の知らない所で存在していたのかもしれない。多分そうだろう。でも、世間で騒がれる程ではなかった。
私はフォークが好きで、専ら、「ガッツ」とか「新譜ジャーナル」等の本に興味が向いた。しかし、何となく、一冊の本を見ていても落ち着かず、あっちこっちと、色々な本に手をつけ、唾をつけたりしていたら、店の旦那に叱られた。落ち着かない理由は、自分自身よくわかっていた。春休みに入って、心にゆとりが出て来た為か、私の胸の内に光り輝く聖子の姿が、再び浮かび始めてきていたのだった。嗚呼!観音様、私はどうすればいいのでしょう。
この小さな書店には、数人の客が絶えず居た。狭いから、客が出入りしたり、移動したりする度に、客同士、互いに肩が当たったり、腰が当たったりした。私はそれが男だと、不愉快で仕方なかったが、女性のソフトな胸や腰のぬくもりが、私の身体に触れると、夢みるような悶えさえ感じた。私は色々な本のページを開いてみたが、結局、最初に手にした「新譜ジャーナル」の頁を開いて、その頃ヒットしていたフォークソング、「愛する少女よ、おまえは処女か!」というヒステリックな歌の楽譜を見ていた。歌手は覚えていないが岡林信康でなかった事だけは覚えている。
その楽譜のコードを見て(私に伴奏ができるかな、歌えるかな)等と独り言のように考えていた時に、何気なく、店の中に入ってくるひとりの女性が、私の視界の片隅に入った。当時の私は、女性に人一倍関心が強く、色気狂いそのものだった。(今の私もその当時と大して変わっていないが…)当然店内に居た女性の全てに、一通りの視線を注いだ。その中でも、今し方入って来たばかりの女性が、私にとっては、一番眼に付いた。私の視線が注がれているのに気付かずにいたその女性は、なんと聖子であった。 (つづく) |
|
| 連載小説「初恋-4」 |
|
|
|
|
1981.6 No.15号掲載
|
|
|
|
私は、彼女が、この書店に入って来た時から、(もしかしたら聖子ではないか)という気配を感じていた。私と聖子との、この偶然の出会いは、私を喜ばせた。(この記念すべき書店は、今も掛川にある)
「やあ、聖子、何買いに来たんだ。」
私が、余りに大声で呼びかけたので、彼女は驚いたらしく、私が居る事に気付いて、私の方を振り向いた時も、澄ました顔で一言、「別に」と言われて私は落胆した。
「なあ、五郎、あいつ知っているか。」
と、私は気まずい思いをして、五郎の方に振り向いて言うと、五郎は、なんだか訳のわからない本に夢中になっていたが、視線を、本から彼女の方に向けて言った。
「俺、知らんなあ。」
と、まるで無関心であった。彼の首筋は、まだ少し赤く腫れていた。
「そうだな、おまえ、あいつと一緒のクラスになった事なかったもんな。」
中学時代、五郎はサッカー部、聖子は英会話のクラブに入っていたのだから、クラブ活動の面においても、二人は縁がなかった。第一、その頃の私たちの学年は八組もあって、私も卒業記念のアルバムで、初めて見るような気がする顔が沢山あった。
私は、五郎から離れて、聖子に近付こうとする分だけ、聖子は、私から遠ざかった。私は必死になって聖子に近付こうと、狭い店内を駆け廻った。しかし、二人の間の距離は、一向に縮まらなかった。私は、咄嗟に、あの入試説明会の時の、彼女の怪訝そうな眼差しを思い浮かべた。私は悲しかった。それを見ていた店内の客(笑い出す者、迷惑そうな顔をする者、その他)の視線で、私は囲まれていた。すると聖子は、態度を急変させて私に近付き、「暫くね。」と、にっこり微笑んで言った。
店内の客は、呆気にとられていた。私も、外見は平静を装いながらも、聖子が、私に対してどういうつもりだったのか、訳がわからなかったし、呆れて返事もできなかった。勿論、狭い店内で二人で鬼ごっこをしたのだから、店員には怒られ、他の客には申し訳なく、二人とも床ばかり見ていた。
「今日、ここへ何しに来たの。」私が、小声で尋ねると、聖子は、
「ちょっとね、最近ベストセラーになった本でね、面白い小説があるって母に聞かされてね、その本買いに来たの。私が読んでも、きっと面白い本よって母は勧めるの。母は友人から借りて、その本読んだらしいのよね。」
「ふーん。」と私は、その頃、小説なんて買って読んだ事もなかったし、ベストセラーという言葉もどういう意味なのかわからず、ただ感心するだけで、後の言葉が出てこなかった。
私は、そんな事を話す聖子に、私の生活とはまるで違う、何だか訳のわからない、聖子の私生活の世界を感じた。聖子の貴品のある容姿は、以前と少しも変わりなかった。私は、何気ない調子で言った。
「聖子、春休み中、一度俺とデートしてくれよ、いいだろう。」
と、しかし、内心は必死の願いであった。
「いいわよ。いつ会うの。」
と、呆気なく返事が返ってきた。
「明日十時、掛川公園のブランコのある、あの広場のベンチの処で会おう。」
「いいわよ、じゃ明日ね。」
(つづく) |
|
| 連載小説「初恋-5」 |
|
|
|
|
1981.7 No.16号掲載
|
|
|
|
私は、(五郎をひとりにしておいて悪かったかな)と、思いつつ、彼の処へ戻った。五郎は、私と聖子の会話については、全く知らなかった。五郎は、もう本屋に飽きたらしく、「おい、真、もう出ようぜ。」と、言っていた。聖子は先程話していた小説を買って、先にこの店を出ていて、店内に聖子の姿はなかった。時計を見たら、もう三時近かった。
昼食を食べ終えて食堂を出たのが、午後一時前でったから、この書店に、二時間余り居た事になる。よくこれだけ長い時間、唯読みさせてくれたと、店の人に感謝してチラッと見ると、店の人はいや〜な顔をしていた。それで、私と五郎は、店の人の熱い視線を感じながら、さり気なく、その書店を出た。
「今からどうしようか。」と、私が尋ねると、五郎は、俯き加減で、余り良い返事は返ってこなかった。「もう帰ろう。」と言いだした。私は、聖子に会えた嬉しさから少し興奮気味で、まだ家に帰る気分ではなかった。すると五郎に、「おまえ、さっきの女性が、好きなんだろう。」と、いきなり言われ、私は、自分の心の中をのぞかれたようで、いくら親友でも、気分を概した。「まあ、そんな事もないけど、一年の時、同じクラスで、仲よかったもんでな。」と、言い返すと、五郎は、私の心の動揺に気付いたらしく、「そんなことどうでもいいよ、もう帰ろう。」と、言って歩き出した。私も一緒に歩きながら、「おお、今日は楽しかったな、また一緒に遊びに行こう。旅行でもしようか。」と、言うと、五郎も、「それもいいな。」と、頷いた。帰り道、二人はそんな遣り取りをして別れた。
私の家は、元来、農家であった。でも私の父は農事を嫌って会社員になっていた。父に春休みはないから、私は、その日、午後四時頃家に帰ったが、父は、まだ帰宅していなかった。父は、いつも、夕方六時過ぎに帰ってくる。私が、家の玄関を開けると、母の声がした。「お帰り、五郎君と一緒で楽しかった?」「只今、別にどうって事ないよ。」と言いながら、私は、二階の自分の部屋に引き籠もってしまった。
六時過ぎになって、父が帰宅してきた。「お〜い、今帰ったぞ、風呂沸いてるか。」と、私の部屋まで、父の声が聞こえた。(多分、父は、そう言いながら、玄関に腰かけて靴を脱いでいるのだろう。いつものパターンなのだから)と、私は思っていた。「は〜い、今、食事の仕度しているのよ、お風呂はもう少しで沸くわ。」母の声が聞こえた。
父は、食前に風呂に入っていると、風呂から出て、湯上がりにはビールを飲みそれから食事をする。父は、食事の間、ほとんど口をきかない。それでも、父は、私に向かって、二言三言話をした。父が何を話したのか、私は覚えていない。私は、食後、母よりも先に風呂に入って、自分の部屋に戻った。(明日十時には、掛川公園で聖子に会える。)私は、そう思いながら寝付いてしまった。私には、兄弟という者がなかった。 (つづく) |
|
| 連載小説「初恋-6」 |
|
|
|
|
1981.8 No.17号掲載
|
|
|
|
翌日、今日も春休みなので、朝食は父や母とは擦れ違いになった。朝八時に起きた私は、すぐに窓を開けて、空を見上げた。空は、晴れ渡っていた。私は、その空に向かって(今日一日、聖子と楽しく過ごすことができますように)と、心から願った。一階に降りて行くと、私は、「お母さん、朝飯用意できてるか。おやじもう出かけたのか。」と、矢継ぎ早に母を呼んだ。それから洗面所に行き、歯を磨き顔を洗った。
食事を済ませて時計を見ると、九時を少し過ぎていた。私の家から掛川公園まで、バスで15分位かかる。私は、昨日と同様に、掛川公園なで歩いて行く事にした。家を出ると、春の日差しが少し眩しかった。
掛川公園とは、町の繁華街の北部の小高い山全体をいう。掛川城跡に作られた公園で、現在、城としての面影を偲ばせる物は、太鼓櫓と、新しく改装された御殿、山頂にある天守台跡、土塁と堀の一部等である。天守台跡には平和観世音が、町を見おろしている。しかし、この観音様は、明治時代、日露戦争に勝利を収めた時、記念に作られたものらしく、当時は、戦勝観世音と呼ばれていたようだ。これは、私の推測に過ぎないが、観音様の台に刻まれた文字で、平和という文字だかが、後で継ぎ足したような痕跡が見られる。敗戦後、先勝観世音が、平和観世音に改められたのだろう。その証拠に、観音様の両脇にある花立ての壺のような物には、今だに、先勝観世音と刻まれている。私が聖子と待ち合わせをしていた頃には、この天守台跡には、消防署の火の見櫓もあったが、今はもうない。この天守台跡まで登ると、町一面が見渡せる。昔は、北を眺めれば田園風景であったのだが、弁財では、都市計画が進行しつつあって、上西郷、倉真の方面に向かって、幅の広い道路が一直線につくられ、大部、住宅も建ち並んでいて、昔とは、様相を異にしている。
私は、公園の約束の場所に着くと、高校進学祝いに貰った腕時計を見た。時計は、午前十時十分前であった。聖子は、まだ来ていなかったので、私は、近くのベンチに腰掛けて、聖子の来るのを待った。
まだ幼い子供たちがブランコや滑り台で遊んでいた。公園の掃除をしている老人もいた。私は、聖子を待ちわびていた。果たして、聖子は来てくれるのだろうか。私は、ベンチの前に立ったり、また腰掛けたりして落ち着かなかった。石段を登ってくる女性を、何度か聖子と見間違えた。
十時から三十分過ぎて、やっと、彼女の姿が、坂の下の方から序々に姿を見せ始めた。彼女は白いセーターを着てジーンズの生地で作られたミニスカートをはいて、手には小さなバスケットを持っていた。
「御免なさい、遅れてしまって、随分待たせちゃったかな。」そう言われては、私の三十分の不安と動揺と怒りの捌け口も失ってしまった。「いや、そんなに待たなかったよ、腰掛けなよ。」と、私が言うと、聖子は、持っていたバスケットを横に置いて、ベンチに腰掛けた。「聖子、映画でも見に行こうか。」と私が言うと、「そうね」と彼女はあまり気が乗らないような返事をした。少し間をおいて、聖子は、「やっぱり、私、こうして暫く真と話をしていたいわ、一年生のときみいたいに。」 (つづく) |
|
| 連載小説「初恋-7」 |
|
|
|
|
1981.9 No.18号掲載
|
|
|
|
私は、暫く何も言わないで、観音様のある山の方を見ていた。
「聖子、昨日買っていった本なあ、どんな小説なんだ。少しは詠み始めているのか。」
「半分位、読んだかな、面白いわよ。女性が主人公なのよね。でも、真が読んでも面白くないわよ、きっと。女性向きよ。あの小説。」
「ふ〜ん、昨日なあ、俺と一緒に居た奴知ってるか、同級生だぜ。」
「そう言われれば、見かけた事あるような着もするけど、私は、よく知らないわ、何ていう人なの。」
「五郎っていうんだ。家は俺のすぐ近くさ。」
それから、二人は、懐かしい一年生の頃の話や、将来の話などで、話題に事欠く事もなく、楽しい時間を過ごした。その間、聖子の顔には、絶えず笑みがこぼれていた。その内に公園内にあるサイレンの音が「ウォーン」と、けたたましい唸りを発して十二時を知らせた。近くで聞くサイレンの音は、耳を劈く(つんざく)ようであった。聖子は両手で耳を押さえていた。
サイレンが鳴り終えると、私は(もう十二時か、早いなあ)と思った。聖子が、「お弁当にしましょうか。」と、言いだした。弁当だなんて言われてたって私は、そんなもの用意してきてはいなかったので、戸惑った。すると、聖子は、自分の持ってきたバスケットの中から、大きなハンカチを取りだして、二人の腰掛けているベンチの私と聖子の間にそのハンカチを広げた。
それから、その上にバスケットの中から、サンドイッチやら、果物やら小さな魔法瓶まで取り出して並べた。そして、私の顔を見て言った。「一緒に食べましょよ。私が作ってきたの、いいでしょ。」私は、突然私の前にお弁当が並べられたので、何も声が出なかった。聖子の好意は、跳び上がる程嬉しかった。(きっと、彼女も、中学一年の同じクラスに居た頃から、私という存在が、彼女の心の中にもあったのだ)と、自分勝手な想像を、私はしていた。
「え〜、聖子が俺の分まで弁当作ってきてくれたのか。」私は歓喜した。聖子の食事をする姿は美しかった。私も、サンドイッチやら果物を食べた。「りんごの皮、むきましょうか。」聖子はそう言いながら、器用にりんごの皮を、果物ナイフでむいた。それを二人して食べた。魔法瓶の中身はオレンジジュースであった。
食事が終わると、聖子は綺麗に、食後の後片付けをして、それをハンカチにくるんで、また、小さなバスケットの中に仕舞った。食後、少し落ち着くと、私は立ち上がって、「いつまでも、ここに腰掛けていても面白くないから、郊外の川の堤へ行って散歩でもしようか。」と、腰掛けている彼女に向かって、私は言った。彼女は、私の顔を見上げながら、不思議そうな顔をして「どうして。」と、尋ねた。 (つづく) |
|
| 連載小説「初恋-8」 |
|
|
|
|
1981.10 No.19号掲載
|
|
|
|
「俺、川の流れを見ているのが好きなんだ。あの日差しに輝いている水面を見ていると、不思議と、心が温まるような気がするんだ。前に、俺、『陽光とせせらぎ』という題の詩を作った事もあるんだぜ。」
「へ〜、真にもそんな趣味あるの。どんな詩なの、それ。」
「へ〜はないだろう。文章は、忘れちゃったけどよ。太陽の光と、小川のせせらぎが会話をするんだ。それを俺が小川の堤に座って聞いている、そんな詩だよ。」
「ふ〜ん、ひとりで聞いているの?」と、言って聖子は黙っていた。(聖子のとって、私が詩を作るなんて、思いもよらなかったんだろう)と、私は思っていた。でも、聖子は、私の誘いに同意してくれた。
「いいわよ、川の堤に行って、日向ぼっこでもしましょうか。」
それで、二人は、中町からバスに乗り私の目指す、目的地に向かった。バスの中はすいていて、五、六人の乗客しかいなかった。それで、二人は、並んで腰掛けることができた。聖子は、何処の川の堤に行くのかは、私に聞かなかった。二人ともバスの中では余り話をしなかった。
バスは、この頃、どの路線バスもほとんど、ワンマンカーになっていた。私と聖子の乗ったバスもワンマンカーであった。私は、目的地の停留所の名まえが、車内にアナウンスされると、近くにあった、押しボタンを押した。バスは、和光橋のたもとで止まった。
「降りるぞ。」と、聖子に言うと、聖子が先に降りて、次に私が降りた。他には、降りる客も乗る客もなかった。バスは、二人を降ろすと、次の停留所へと走り去って行った。和光橋の下には逆川が流れていた。決して、澄んで綺麗な流れとは言えなかった。春とはいえ、まだ三月の下旬。逆川の堤の草たちは、まだ枯れていた。河沿いの堤を上流に向かって、今度は私が先に歩いた。聖子は黙って私の後ろからついてきた。
「聖子、寒くない?」私は振り返って、聖子に尋ねると、
「そんな事ないわ、今日は、お天気もいいし、暖かくて風もないわ。」聖子は微笑んで言った。私は、また暫く、黙って、逆川の流れを見ながら堤を歩いた。
「俺、小学校の頃、この川でよく釣りをしたんだぜ。」
「そう、真、釣りが好きなの。」
「釣りも、魚が釣れれば面白いんだけどな、釣れないと、すぐいやになっちゃうよ。最近は、釣りもしないなあ。」
二人は、橋のたもとから、五百メートルくらい離れた処で、堤の中程まで下がっていった。そこで、二人は、枯れ草の上に腰をおろした。堤は、誰が草刈りをしてくれたのか、さっぱりとしていた。
「おい、大の字になって空でも眺めようか。」
「いいわね。」二人で笑いながら仰向きに寝た。
「空が、青いなあ。」
「そうね…。でも、さっきね、真が公園で話してくれた詩ね、どんなのか、読んでみないとわからないけど、真の話から、大体の詩の情景は浮かぶのよね。なんだか、孤独で寂しい感じがするわ。線が細いのよ。もっと、力強い詩を書きなさいよ。」聖子は、時折訳のわからない事を言って、私を驚かせた。
「そうかなあ。」と、言いながらも、私にはわからなかった。
(つづく) |
|
| 連載小説「初恋-最終回」 |
|
|
|
|
1981.11 No.20号掲載
|
|
|
|
私は、仰向けになって寝ている聖子の横顔を見た。聖子の髪は、ショートカットであった。顔は、どこか垢抜けしていて色白であった。しかし、そんな事より、どうも先程から聖子のミニスカートが、気になっていた。ミニスカートの中から、聖子の真白なパンティーが見えそうで見えない。最も聖子のパンティーが白だったかどうか私にはわからないが…。一層の事、ちょっとでいいから、ミニスカートの下の、聖子のパンティー見せてくれといいたい気分であった。
「聖子、これからもこうして、時々会ってくれるか。」私は、空を見ながら話した。
「いいわよ。真、昨日買った本ね、私が読み終えたら貸してあげようか。面白くないかもしれないけど。」
「うん、貸してくれ、面白くなかったら、すぐ返すよ。」
「聖子、こっち向けよ。」
「な〜に?」
二人の視線が、一瞬合ったかと思うと、聖子は、すぐまた、天空を仰いだ。
「聖子って、奇麗だなあ。」聖子は何も言わなかった。暫くして、
「一年の時の真って、すごく優しかった。」聖子が言った。
それからは、会話がとぎれてしまった。逆川の岸辺で、二人は、初めてのキスをした。私にとって忘れられない、清潔なキスの味であった。逆川の、川の流れは決して澄んでいなかったが、それでも水面は春の日差しを浴びて、シャンデリアのように光り輝いていた。聖子は、起き上がって、膝小僧を抱えて座っていた。聖子が、物静かに囁いた。
「真、ほら、紋白蝶よ、もう紋白蝶が舞っているわ。二匹いるわよ。ランデブーしている。でも、もう少し春らしくならないと、蝶も、蝶の美しさが、自然の中で映えないわね。」
段々と、聖子の話が難解になってきた。私は何も言えなかった。
「もう、帰ろう。」
私は、聖子の優しさの中で、幸福な一日を過ごすことができた。時計を見ると、もう午後四時を過ぎていた。
後日、聖子から、私当てに、一通の手紙がとどいた。読んでみると、「私、妊娠しました…。」と、書いてあった。私は、愕然とした。『冗談言うな!キスしただけで、何故妊娠するんだ。』あの初恋の女性の心理は、私にとって今だに謎である。彼女は、いつも、何かを見詰めていた。それが何なのか、私にはわからない。しかし、その手紙の中に同封してあった、聖子の一篇の詩から、私にも、聖子の心の一部を理解できるような気がした。その、聖子の詩を、読者の皆さんに紹介して、このちっぽけな、小説とはとても言えないような、連載物の幕を閉じるとする。 |
|
|
賛歌(ランデブーする蝶)
蝶は知らない
この世の、空しさと悲しさ
蝶よ
おまえたちが
蛾のようであったなら
こんなにも、愛されないであろうが
美しい蝶よ
か弱い蝶よ
春の新緑の中で
無言で語り合う、おまえたち
ひら ひら ひら
嗚呼!
また、おまえたちの仲間が
ひとつ隣の菜の花にとまり
無言のうちに、何かを語り合っている
(聖子より愛をこめて 真さんへ) |
|
|
長い間、私の拙い文章を読み続けて下さった方々には、作者より、深く感謝いたします。また、この物語を掲載させてくれる機会を与えて下さった、編集者の方々にも感謝いたします。ありがとうございました。
- Good-bye See you again - |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|