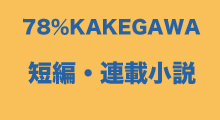 |
 |
|
|
短編小説「肉」 |
|
|
|
|
|
|
1980.6 No.3号掲載
|
|
|
|
|
作:田辺 勇
|
|
五月の蒸し暑い晩、勇の乗った電車が駅まで百メートル余りの踏み切り辺りで急停車した。混だ車内のざわめきの中で、放課後のクラブ活動の疲れを身体に感じていた勇は、焦りが胸の中に萌え上がるのを知った。おそろしく長い五分後に、車内アナウンスが事故を告げた時も、四十分経って電車が駅に滑り込んだ時も、何かイライラするものだけを体に感じていた。線路の脇の小道を自転車を引っぱって、とにかく夕食は肉があるといいなと思いながら、ふくらはぎの張る足を家に向かって運んだ。
帰宅の通り道ならいくつもあるのにその道を選んだのは、慣習であった。事故現場はいつもの踏み切りの静けさと様子が違っていた。勇は変だなと思った。さっき、何故帰り道の事を考えなかったのだろうと思った。
人々の言葉にならない声々が低く耳に伝わってきた時、そこに死体のある事を予感させた。複雑な気持ちになっていた。人の群れに二十メートルの所で立ち止まって線路の上を眺めた。夜気に包まれた線路の上は写真のように静かであった。
何も見えないと思ったその時、自分の足下に確実に生き物が潜んでいる事を感じた。が、瞬時の後、その塊が「かつて生きていたもの」であると判断できた。赤ん坊であった。上向きの顔の左下にひとすじの細い赤黒い線が走っていた。静かな対面でもあった。
勇は、かわいそうとも悲しいとも思う事が出来なかった。疲れが少しずつ体のなかに蘇るのを感じた。死という感覚が、それを目の前に置かれてもピンと来ないのが何のせいなのかわからなかった。
しばらくの後に家に向かって歩き出した勇の頭は混乱し、体は食べ物を求めていた。口が「みにくい」という言葉を虚ろに繰り返しながら家についた。
家族に事故だよとポツンと言って勇はひたすら夕食の刺身を口に運んだ。 |
|
|
|
短編小説「十八」 |
|
|
|
|
1980.7 No.4号掲載
|
|
|
|
|
作:田辺 勇
|
|
浜は思ったよりも風が強かった。
昨夜。和夫から明日海に行かないかと誘われたとき、なんとなくうんと答えたものの気の弾まなかった自分が思い出された。和夫と来ても同じだったかも知れない。和夫は今朝、急に用事が出来たと電話で謝ってきた。やめようかどうしようか迷っているうちに、黙って家を出ていた。50ccのバイクに乗っていた間は時間を忘れていたが、防砂堤に立った時から時間が気になって仕方がなかった。腕時計を忘れて来ていたが、浜の空気は午前中の臭いがしていた。
浜は、小さな女の子をつれた若夫婦以外は波の打ち返す音と風だけだった。沖を通る漁船も一つもなかった。軽く弧を描く水平線を見ていると、言い出す理由がわからない自分が、あの線の向こうにもいる気がしてきた。煙草を取り出して吸った。煙がすぐ消えてしまってまずかった。
浜に腰を降ろして、何も考えないようにしようと思えば思う程、このひと月の事が浮かんで来た。この日曜に、独りで海にいる自分がつらかった。やるせない午後を思っていた。
ふと若夫婦を見た。夫婦は笑いながら何かを話している。女の子は波の打ち引きに夢中で、駆け回っている。と、その子が転んだ。夫婦は見ていた筈なのだが、動こうとしなかった。女の子は泣かなかった。立ち上がって砂を払うとこっちを見た。自分と視線が合うと小さな笑いをその頬に見せた。自分もつられて笑う素振りをしていた。女の子はすぐに振り返ると夫婦の方へ走っていった。
僕はここにいられない自分を急に感じた。ここで午後を向かえてはいけないと思った。今日話さない限り、もう話す時はないと確信した。自分が何故ここへ来たのか話そう。何故啓子でなくちゃいけないのかも話そう。いや、今日会わなくっちゃいけない。
バイクに向かって駆け出した時、陽は既に真上に来ていた。
月曜、啓子は学校を休んでいた。僕は十八になっていた。 |
|
| 短編小説「血」 |
|
|
|
|
|
1980.8 No.5号掲載
|
|
|
|
|
作:田辺 勇
|
|
僕の生まれた村は、海岸に面した全部で十戸ばかりの小さな村だったので、小学校へ行くまでは僕の遊びといえばひどく寂しいものだった。弟は、僕と5つも年が違っていたので相手にならなかったし、近所には同じ年の子供がまるっきりいなかった。だから小学校へ行くのが楽しみでならなかったのだけれどその入学式を迎える前の晩に漁夫の父が僕に言ったことばは、その時の僕には何の事かよくわからなかったが、考えてみれば僕のその後の人生を大きく左右させたことばかも知れない。
僕は小学校時代は、持前の引っ込み思案から、父の心配したような「経験」に出会う事はなかった。けれど中学生になってまもなく、僕は顔にニキビを作るようになった。髪を伸ばす事も覚えた。知らず知らずのうちに、僕は父の心配する方向へ向かおうとしていたのだ。その年に、僕が中学一年の夏に弟は風邪がもとであっけなく死んでしまった。中学が一年過ぎると、僕は同じクラスの栗毛の髪の美しい少女に夢中になっていた。待ち合わせをする事も度重なった。僕は父にその事を知られたくはなかったので秘密にしていた。しかし、恋は長続きしなかった。僕は、僕の得たいの知れない何かにひどく恐れた。
僕は中学を卒業すると、すぐに父の元で働いた。失った恋についてはもう思い出す事もなかった。僕は小さなポンプ船で沖に出る毎日に、物足りない何かを感じ始めていた。僕は必要なものは、あの外の世界に転がっているんだと思った。僕が漁に出て三年目に父は帰らぬ人となった。僕はとうとう一人になった自分を思うと気が楽なような、寂しいような思いだった。僕は船を捨てることにした。街に出て行く事にした。
僕は煙の絶えない街で三年目になって、やっと父が僕に言おうとしていた事がわかった気がした。僕の体に流れる血をひどく怨んだ。僕はその後二年毎に職場を変えた。そして僕は、三十になる前の週に僕の死の日を決めた。 |
|
|
短編小説「進路・秋・人生」 |
|
|
|
|
1980.9 No.6号掲載
|
|
|
|
|
作:田辺 勇
|
|
帰りのバスで、丁度和夫と乗り合わせた。三年になって、和夫とはクラスも変わったのであまり顔を合わす事もなくなっていたが、和夫は眼でちょっと挨拶すると隣にやって来た。
「俺、やっぱり大学へ行く事にしたよ。」
また進路の話しかと思うとうんざりした。
「俺は、…まだ決めてない。」
本当はもう担任と話しをしてあった。けれど自分の事として進路が具体化していく内に、気持ちの方はずんずんと重くなっていった。担任との話を親に打ち明けた時も、なんだか嘘をついているような気になったり、終いには投げ遣りな自分を嫌だなと思いながら坐っていたのを思い出す。
「お前は相変わらずだなぁ。いつもなんだかんだと言う癖に、悠長なもんだよ。」
和夫は、思った事はすぐに口に出してしまうタイプだ。そんな性格は知っていた筈なのに反射的にむかっとしてしまった。言葉を返そうと探ったけど見つからないので窓の外の流れる景色に目を向けた。
最近の自分はいつもこうだ。人と出合う、話をする、面白くない、むかっとする。みんな自分の所為だとわかっていながら人を気まずくさせたは、またやってしまったと思う。幸いに、和夫は何も感じなかったようだが、そんな態度にさえすぐに腹を立ててしまう。すべてが進路の所為だと括りつけたいが、自分には何も見えないのだ。こんな「時」は、早く過ぎてしまえばいいと思うが、一体過ぎるという事がどういう事かわからない。
「おい、着いたぞ。何ぼんやりしているんだ、早くしないと汽車に乗り遅れるぞ。」
和夫は、そう言うと定期を手にして人ゴミを分けていった。のそのそと人の後についていくと、バスの窓から走って行く和夫の後ろ姿が見えた。自分は腹を立てていた筈なのに結局ぼんやりとしていた。和夫は改札口でこちらを振り返ると手を振り、白い歯を見せた。自分も手だけ振って返した。
バスを降りて、駅に向かって歩いて行くと、頭の中は空っぽになってしまった気がした。きっと空っぽの頭の中を、汽車が轟音を響かせて駆け抜けて行くのだ。 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|